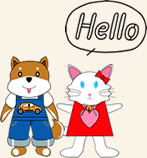
これは、ご縁あって出会い、大切な人生に関わらせていただいた患者さまやそのご家族さまとの思い出の記録です。
今、同じようなご病気や状態で療養されておられる方々、介護されておられる方々や、いずれは誰もが歩む道としてご自身の老いや生き方を模索されておられる皆さまの一つの指針になることを願い、綴っていこうと思います。
診療日誌に登場する患者さまには、それぞれ病名がありますが、私たちは「病気」だけを診るのではなく、その方の「人生」をみる医療者でありたいと考えています。私たちが出会った『天晴れ(あっぱれ)人生』を皆さまにも感じていただければ嬉しく思います。

犬と車が大好きな院長は、
毎日、黄色い車で訪問しています。

自由奔放な猫好きの副院長は、
ときどき訪問しています。
89歳男性 パーキンソン病

誤嚥性肺炎で入院され、その退院後、寝たきり状態になったことをきっかけに、通院できなくなり、訪問診療のご依頼をいただきました。
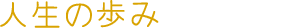
四国のお寺のご出身で、関西に出てご自身で会社を立ち上げ、寝たきりになるまでは会長職として経営に関わるなど活躍されておられました。多くの従業員を雇われておられる責任感からか、以前は、体調の変化があれば、すぐに病院を受診し、早期胃がんも手術して治癒するなど、健康に気をくばられていたそうです。
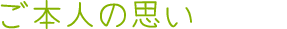
「再び、誤嚥性肺炎になっても入院はしたくない。しかし、家族に迷惑がかかるのであれば、その時は入院も考えようと思うが、基本的には家にいたい。」
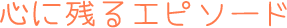
退院後、寝たきり状態ではありましたが、近所の川沿いに咲く大好きな桜を見るためにリハビリに励み、1年後には車いすで見に行くことができるようにもなりました。
やがてご飯があまり食べられなくなり、眠ったり、ボーっと過ごされることが多くなりました。そうして3か月経過したころ、とうとう水分さえもほとんど摂れなくなりました。しかし、水分摂取ができなくなってから、逆に、ご本人の意識はしっかりとされ、ご家族に「自分は病気になれば治療をするのが当たり前でそのようにしてきたが、これ以上は体がかわいそう」「最期が近い」「向こうで母親に会えるので楽しみにしている」など、いろんなお話しをされました。
ご家族は、点滴などの延命を望まないご本人の意思を尊重するつもりでいましたが、気持ちの整理がつき切らず、点滴を希望され、ご本人とご家族で話し合いをしました。私としてはご本人とご家族双方の気持ちを汲んで、「ご家族のお気持ちに応えて、少しだけ点滴をしますか?」とご本人にお尋ねしたところ、「わかった」とお答えされたので、点滴を施行することになりました。
翌朝、訪問すると、痰が増え、苦しそうにされている様子をみて、ご家族は「もう点滴は結構です」とおっしゃいました。ご本人はすっかり声もかすれていましたが、そんなご家族の心情を察して、小声ながらに「楽になった」とおっしゃり、「オールOK」と繰り返されるのでした。その翌日、ご家族に見守られ、旅立たれました。 49日を迎えた頃、線香を手向けに訪問させていただきました。ご家族のお顔には柔らかな笑顔が見られ、遺影はご葬儀の時と同じ笑顔のご本人の写真ですが、遺影には映っていなかったご本人の手のOKサインがありました。葬儀屋さんが加工して消されていたトレードマークの「オールOK」が、この方の人生そのものを語っているようでした。
91歳女性 老衰

同居の娘さんから「母が数日前から左の手足が動きにくくなり、介助しないとトイレに行くことができなくなったので訪問診療に来てもらいたい」と電話がありました。
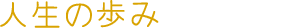
生まれつき病弱ながらも戦禍を生き抜き、ハルピンで終戦を迎えられたそうです。引き上げの時の周りの人たちの温かい支えあいなども自叙伝に記され、数年前に出版されていました。その著書から「私は何かを成しえた訳でもなく平凡な女性として生きてきましたが、思春期は戦争という異常事態の真っ只中で過ごしました」―本や勉強が大好きだった少女時代を経て、時代に翻弄されながらも人に恵まれた人生にずっと感謝されていました。
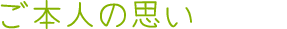
ご本人と娘さんは、数日前から出現した片麻痺について、脳血管障害の可能性があることに気がついておられましたが、病院に行って治療することは望んでおらず、「今は娘や犬に囲まれているのんびりした環境で、好きな万葉集を読んだりして療養しています。脳梗塞という診断がついて病人として病院に入院するのではなく、家でこの生活を続けたい」という強いご希望でした。
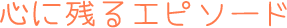
だんだんと下肢に力が入らなくなり、立つこともできなくなってきましたが、その都度、病院での加療か、家での療養か、どちらをご希望されるのか確認しました。ご本人もご家族も一貫して、在宅での療養しか選択肢にはなく、全くぶれることがありませんでした。
3か月後には睡眠時間が増えていき、水分摂取量が少ないために、膀胱炎による発熱で食欲の低下も進行しました。それでも、家での療養を継続するご意思は変わりませんでした。
8か月後には微熱が数日続き、全く食事を受けつけなくなってから2日後に、眠るように静かに永眠されました。
49日を過ぎたころ、家にお参りに行かせていただきました。ちょうどその頃、私どもが作成した『マンガで考える在宅医療の選択、家族の生活はどうなる?』を発行したので、お持ちしてお渡ししました。すると、小誌を読んでくださった娘さんから「実は、母の意に沿いつつも、これでよかったのだろうかと一抹の不安があったのですが、自分たちの選択はよかったのだと納得ができました。自然に逝きたいという思いを叶えることができて本当に良かったです」とご連絡をいただきました。死亡診断書には、時代に翻弄されながらも生き切った91年の人生に敬意をもって「老衰」と書かせていただいたことについても、ご家族は「死因を病気ではなく、老衰と書いていただけたことが嬉しかった」とおっしゃっておられました。本物の大往生でした。

最期の最期まで、ぶれずに自然に抗わない生き方を選び、療養されていたことに頭が下がります。

あれだけぶれずに人生の選択をされていても、ご家族には不安や葛藤があったことを後から知り驚きましたが、思いを尊重してくれたご家族に感謝されながら、きっとそばで見守っておられるのではないかと感じました。
88歳男性 老衰

医者嫌いでかかりつけ医もなく、だんだん体が動かなくなり、介護されていた奥さんが困り果て、クリニックに相談に来られました。
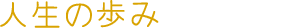
研究熱心で人望も厚く教え子たちにも慕われた学者人生を歩み、退職後は毎日のように図書館に通い、一日中、借りた本を読んで過ごす生活をされていました。
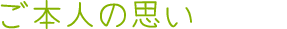
「体に変化があっても、病院には行かず、そのまま家で死にたい。もうやり切ったので、いつ死んでもいいと思っている。自分が思うように逝きたい。」と強く希望され、急に体調が悪くなったとき、救急車を呼ぼうとする奥さんを全力で阻止することもしばしばあったようです。
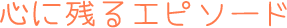
膝の痛みを抱える奥さんが、ある日、突然クリニックに何㎞も歩いて来られました。お話を伺うと、これまではなんとかトイレなどに行けていたものの、今は布団から出るのも一苦労されているご様子でした。とても頑固な医者嫌いということでしたので、まずは、介護保険サービスを利用して、訪問看護師さんやケアマネージャーさんの力を借りようと思いました。そうしたケアスタッフが関わるようになり1か月くらい経ったころ、ご本人が少し笑うようになったと奥さんが喜ばれ、「ふたりとも死ぬことばっかりだったのが、生きることを考えるようになりました」とおっしゃっていました。その後、奥さんの言葉通り、食事もよく食べて、活気もあり、嫌がっていたお風呂にも入ることができました。そんな落ち着いた状況が半年くらい続きました。
関わり始めた当初、本人の意識がなくなるようなことがあれば救急車で病院に運びたいとおっしゃっていた奥さんでしたが、ある朝、発熱したご本人にプリンやアイスクリームなど口当たりの良いものを食べてもらい、少し休んだ午後、脈が触れていないことに気がつきました。しかし、救急車を呼ぶことはせず、ご本人の意思を尊重して、家で見送られました。

自宅で自然な最期を迎えられても、かかりつけの医師がいなければ、救急車か警察を呼ぶことになってしまいます。ご本人の「医者不要」の生き方を貫くお手伝いができたことに、医師として誇りを感じています。

こんなに徹底した医者嫌いのご本人の最期が病院になるのは気の毒だと思っていましたが、訪問看護師さんやケアマネさんと一緒にみんなでご夫婦を支えることができました。でも、一番頑張られたのは何より奥さんに違いありません。
85歳女性 パーキンソン病

肺炎で入院されていた病院からのご紹介で、当院の訪問診療が始まりました。
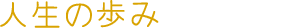
一家の主婦として家のことはもちろん、ご主人が営む食堂の切り盛りもされておられました。いつも笑顔を絶やさず、いやごと一つ言わない穏やかな人柄で、誰からも慕われる看板女将は美しい花々や美味しい食べ物が大好きでした。
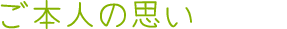
できるだけ余計な薬は飲まないほうが良いという信念をもっておられ、ほとんど会話ができない状態で退院された当初、病院で大量に処方されていた薬を少しずつ減らす提案をしたところ、手をたたいて喜んでおられました。
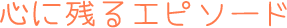
寝たきりの状態でおうちに戻られてからは、料理人であるご主人が作る食事をたくさん食べられ、食欲も回復し、娘さんやお孫さんに囲まれて和やかに過ごしておられました。ご主人は、介護のためにしばらく食堂を休業していましたが、年齢的な節目もあって、いよいよ閉店しようと決意された最後の2か月、期間限定で営業を再開することにしました。当時、ご本人は時折、発熱して体調を崩すことがあったのですが、営業再開期間は一度も体調を崩すことなく、お店に立つご主人と娘さんをバックアップされるという、看板女将ぶりは健在でした。久しぶりの味を楽しみに来店される常連客の皆さんからのエールにも応えるかのように、無事に営業再開期間を終え、長く地域に愛された看板女将の食堂は幕を閉じられたのです。
少しホッとされたのか、お店を閉じてから間もなく、誤嚥性肺炎と思われる発熱が続きましたが、次なる目標は「大好きな中華料理をみんなで食べに行くこと」でした。以前、発熱を繰り返しながらも、自然と、花の季節には発熱の頻度が減り、ストレッチャーでお花見に行くことができたので、きっと今回も大丈夫だろうと期待していたら、案の定、熱がさがり、ご家族全員と私どもも一緒にみんなで中華料理の円卓を囲むことができました。翌日、訪問看護師さんに「すごく美味しかった」と嬉しそうに話されていたそうです。

病院であれば100%許可されないような全身状態で、外に連れて行こうとする主治医もまずいないと思いますが、何よりも、ご家族が一丸となり万難を排して食べに出かけることを実現させた愛情に脱帽です。

大好物のクリームパンを差し入れさせていただくと、「ペロッと2つも食べました!」と言う娘さんの嬉しそうなお顔を見て、家業でもある「食」を大切に生きてこられたご本人の人生を感じ、その最期の時間を共に過ごさせていただけたことに感謝しています。
この診療日誌は、登場する方々のご家族の承諾を得て、綴らせていただいております。
お誕生日の時はアフロの被り物で笑わせてくれたり、サービス精神旺盛で、とても思いやりのある素敵な方でした。訪問診療で関わることができ、いい時間を共有させていただきました。
ご家族の前では楽になったとおっしゃり、人生を振り返り「オールOK」と言い残して、旅立たれた生き様にご家族はどれだけ勇気づけられたことでしょう。私もそんな人生を目指したいです。